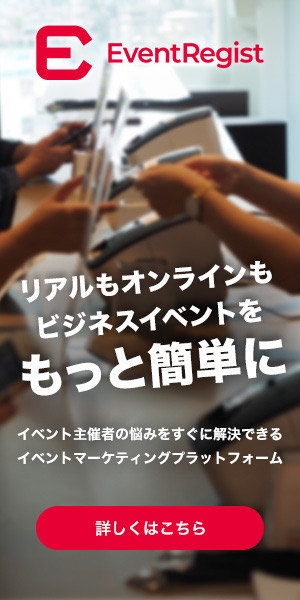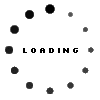想いを形にするテクノロジー 株式会社デナリパム 井本 直正さん

コースケよーこのミュートを解除 第137回 2023年1月19日(金)12:00〜
株式会社デナリパム創業者兼代表取締役の井本直正さんをゲストに迎え、彼の技術的な取り組みとその応用について詳しくお話を伺いました。井本さんは30年以上にわたり、コンピュータ技術の進化とともにキャリアを築いてきました。彼の会社デナリパムは、先端技術の研究開発を中心に、産官学連携や企業のDX推進を支援しています。
井本さんは、コンピュータ技術の変遷を振り返りながら、技術の小型化と進化について説明しました。特に、AI、AR、VR、メタバースといった最新技術の活用が広がっていることを強調し、それが社会課題の解決にも寄与していると述べました。
番組中盤では、井本さんが関わる「産学連携プロジェクト」について紹介がありました。このプロジェクトでは、学校や企業と連携し、学生たちが実際にAIやメタバース技術を用いたアプリケーションを開発・提案する場を提供しています。具体的には、企業のホームページをメタバースに変換したり、大型機械をVRで体験できるようにするなどの取り組みが行われました。
また、デナリパムが開発した「ビジョンコントローラー」も紹介されました。これは、カメラを使って手の動きを認識し、インタラクティブに映像を操作する技術で、展示会などでの利用が期待されています。井本さんは、この技術を通じて、より多くの人々が最新技術を身近に感じ、活用できるようになることを目指していると語りました。
最後に、井本さんは3月22日に大阪南港ATCで開催されるセミナーの告知を行いました。このセミナーでは、学生たちが開発したロボット技術や遠隔操作のデモンストレーションが行われる予定です。
今回のトークショウでは、井本さんの情熱と技術への深い理解が垣間見える内容で、非常に興味深いものでした。
AI、ロボティクス、IoT、5G、Edtech、ITなど最新テックでビジネスを支援するデナパリズムの井本さん。その活動と最新技術が世界をイベントをどう変えるか。おうかがいします。
AI
AIモデル開発から、TensolFlow.jsなどを使用したブラウザで利用できるAIシステムの開発、 グラフや地図などで様々な分析ができる、AIエッジシステムのエーアイスタータなどを開発しております
ロボティクス
AIやIoT、ロボティクスの技術を組み合わせた、 等身大のコミュニケーションデバイス、デナポータルや、 マイクロモビリティ、デナホバーの研究開発をおこなっています
IoT
M5StickVなどのAIチップと様々なセンサーを内蔵した、超小型AI+IoTデバイスの研究や、 BLEビーコンを使用した位置情報検知システムなどの開発しております
5G
5G X LAB OSAKAを、共同運営される大阪市さま、大阪産業局さま、 ソフトバンクさまの支援のもとで、5Gを活用した、さまざまな産業の イノベーションにつながる、研究開発を日々おこなっています
EdTech
学校法人や自治体などに、AI・ロボット・IoT・VR・ARを学べる教材の提供や、講義・講演サービスの提供を行っています
IT
基幹系システム(販売・仕入・在庫・生産)、 情報系システム(ナレッジマネジメント・コラボレーション・ローコード開発)、 モバイル・タブレット・ウェブシステムの企画から開発、導入支援を行っています
動画URL:https://www.youtube.com/embed/tPIE1Yn7MeE
文字おこし
(AIによる文字おこしのため誤字・脱字あります)
「コースケ・よーこのミュートを解除」。はい、皆さんこんにちは、イベントマーケティングのよーこです。こんにちは、イベントレジストのコースケです。2月9日、第140回目の「コースケ・よーこのミュートを解除」が始まりました。この番組は、イベントレジストのヒラヤマコウスケさんとイベントマーケティングの樋口陽子が、イベントの中の人やプロフェッショナルをゲストにお呼びしてお話しする番組です。その道のプロだからこそ語れるリアルな価値やイベントの魅力をお話しいただきます。
さて、最近はApple初のXRプロジェクトの投稿をよく見かけます。私はまだ体験していませんが、コースケさんは何か体験されましたか?
コースケ:まだ体験していないんですけれども、あれが今後の未来の形になるのかなと思いますね。本当に革新的な技術で、コンタクトレンズのようになるともっとすごいことになりそうです。
よーこ:そうですね。展示会などで研究分野でもどんどん活用されているのを見かけます。古いMRデバイスでもすごい体験でした。先端技術に触れるのは楽しいですよね。今日はそんな先端技術を軸に活動されている方をゲストにお呼びしました。では早速ご紹介します。株式会社デナリパムの創業者兼代表取締役、井本直正さんです。こんにちは。
井本:こんにちは、よろしくお願いします。
よーこ:今日は井本さんに「想いを技術で形にする」というテーマで、現在のご活動とイベントへの活用の可能性についてお話を伺います。よろしくお願いします。
井本:よろしくお願いします。
よーこ:今日はどちらからご参加いただいているのでしょうか?
井本:ここは大阪南港ATCというところで、会場の隣にある先端技術系の企業が集まるオフィスです。大阪市が管理している場所で、そこの放送室をお借りしています。
よーこ:ありがとうございます。大阪の先端技術の拠点からご参加いただいているんですね。事前に頂いたプロフィールを拝見したところ、企業や教育の場で幅広く活動されているとのことでしたが、現在の活動に至るまでの経緯を簡単にご紹介いただけますか?
井本:はい、ありがとうございます。改めまして、株式会社デナリパムの創業者兼代表取締役の井本直正です。よろしくお願いします。私は30年から40年前からコンピューターに関わってきました。パナソニックや石川島播磨重工業などと直接取引し、新しい技術を使った様々なプロジェクトを手掛けてきました。現在も役員を務める会社があり、そちらでも同様に技術を活用した事業を進めています。
そこでは、ソフトハウスとして依頼を受けた仕事に対してその結果を納品するという形のビジネスを行っていました。しかし、私自身や私の周りの人々に蓄積されていく様々な技術や先端技術をもっと活用したいという思いがありました。そのため、会社を役員として務めながら新たに株式会社デナリパムを立ち上げ、現在に至ります。デナリパムは今年で10年目となります。
デナリパムでは、先端技術の研究開発を中心に活動しており、産学官連携で学校や大阪市、自治体、企業のDX技術開発などをお手伝いしています。コンピューターに関わる全てのことを行っており、パソコンの製造、データセンターのサーバー構築、システム開発、生産販売物流、タブレットやiPhoneのアプリ開発など、多岐にわたる分野で活動しています。例えば、名刺を変形させるアプリを作ったり、AR、VR、XRの技術開発も手掛けています。来たボールは全て打ち返しているような感じで、幅広い技術に対応しています。
よーこ:デナリパムは10年ということですが、「デナリパム」という名前の由来は何ですか?
井本:よく聞かれます。本当にありがとうございます。「デナリパム」は、ラテン語の「デナリムリパーム」から来ており、貯金箱を崩した内容を意味しています。私が子供の頃から持っていた貯金箱の中にはお金ではなく、おもちゃや様々なアイテムが詰まっていました。例えば、どこかで拾った鍵や工事現場にあったものなど、宝物のように大切にしていたものが入っています。今見るとちょっとぞっとしますが、それらは私にとって大切な思い出です。
デナリパムの名前には、技術をいっぱい詰め込んだ箱をお客様に提供し、それを使ってお客様が何をするかをテーマにしています。私たちは技術バッターであり、本当にやりたいことやできることはお客様が持っています。そのお手伝いをするスタイルで、製品や物を売るのではなく、一緒にやっていきましょうという姿勢で活動しています。
コンピューターも30〜40年前から現在に至るまで大きく変わりました。最初はとても大きかったんですよね。それがどんどんPCに入り、スマホに入り、そして今では空間の方にもコンピューティングが広がっていっています。その変遷をずっとご覧になっていらっしゃると思いますが、小型化していくことで最新技術の可能性も広がっているのでしょうか?
井本:おっしゃる通りです。昔は雑居ビルの一室をコンピューターのCPUが占めていました。私がスタートした時は、フロア全体がコンピュータールームで、そこにCPUがたくさんありました。そのCPUの隙間に椅子を置いて、監視カメラにバレないように昼寝をしたりしていました。若い頃の話ですが、フリーアクセスという床に配線するための設備があり、そこにお弁当を置いて腐らないようにしたりしていました。
今では、コンピューターはデスクトップからさらに小型化し、AIを搭載した手のひらサイズのものになっています。しかし、その技術を理解し使いこなせる人が減っているのも現実です。パソコンが普及した時も使える人と使えない人がいましたが、スマホやインターネット、そして今ではAIに関しても同様に、できる人とできない人、やる人とやらない人が分かれてきています。
それが社会課題となっており、私たちはその技術を分かりやすく伝えることもミッションだと考えています。便利になり自由度が高くなった技術をどう活用するかをサポートすることも重要です。セミナーや学校の講義、顧問としての情報共有などを通じて技術を広めています。
よーこ:なるほど。最近も産学連携プロジェクトの発表をされたと伺っていますが、直近の活動について教えていただけますか?
井本:ありがとうございます。直近では、2月の初めに産学連携プロジェクトを発表しました。このプロジェクトでは、学校や企業、大阪市様のお手伝いをいただきながら進めてきたものです。
そういった形でプロジェクトを進めています。例えば、学生たちが最新技術を学び、それを実際の企業でのプロジェクトに応用することで、実践的なスキルを身につけることができます。また、企業側も新しい視点やアイデアを取り入れることで、新しい製品やサービスの開発につなげることができます。
さらに、私たちは技術だけでなく、その技術をどのように活用するかという部分も重要視しています。例えば、イベントの分野ではARやVR、XRといった先端技術を使って、参加者に新しい体験を提供することができます。これにより、従来のイベントとは一線を画す、より魅力的でインタラクティブなイベントを実現できます。
よーこ:それはとても興味深いですね。具体的にはどのような事例がありますか?
井本:例えば、私たちが手掛けたプロジェクトの一つに、大規模な展示会でのAR体験があります。参加者がスマートフォンやタブレットを使って展示物にかざすと、画面上に関連する情報や3Dモデルが表示される仕組みです。これにより、参加者はより深く展示内容を理解することができ、体験の質が向上します。
また、VRを使ったバーチャルツアーも提供しています。遠隔地からでもイベントに参加できるようにし、リアルな会場体験をオンラインで実現しています。これにより、参加者の地理的な制約を取り払い、より多くの人々にイベントを楽しんでもらうことができます。
よーこ:なるほど、技術を使ってイベントの枠を超えた新しい体験を提供しているんですね。それは参加者にとっても、主催者にとっても大きなメリットですね。
井本:そうですね。技術を活用することで、参加者の満足度を高め、主催者にとっても新しい価値を提供できると考えています。私たちの目標は、技術を使って人々の生活をより豊かにすることです。そのために、これからも新しい技術の研究開発を続けていきたいと思います。
井本:ありがとうございます。こちらがTwitter、今はXですね、で共有した山岳連携プロジェクトの内容です。このプロジェクトは、私が複数の学校で顧問や講義をしている中で、賛同いただいた学校とともに実施しました。今回は、東洋機械金属株式会社という当初プライムの企業様がテーマを提供してくださり、そのテーマに基づいて学生たちが取り組みました。
2月3日に発表会があり、全てのデザインやプレゼンテーション、司会などは学生たちが担当しました。特に声優志望の学生やYouTuber、VTuberを目指す学生たちが積極的に参加してくれました。
樋口:デジタルネイティブな世代ならではの取り組みですね。具体的にはどのような技術発表があったのでしょうか?
井本:ありがとうございます。東洋機械金属株式会社様は、創立100周年を迎えるにあたり、ホームページの改善を希望されました。学生たちは授業で学んだメタバース、VR、AIの技術を活用し、単にホームページを改善するだけでなく、完全にメタバースに変える提案なども行いました。また、同社の大きな製品をデジタルツイン化し、仮想空間で体験できるようにしました。
このプロジェクトの特徴は、提案だけでなく実際に動くアプリケーションも作成し、企業に提案する点です。実際に動くものを作ることで、学生たちはより実践的なスキルを身につけることができました。
樋口:それは素晴らしいですね。アイデアソンとハッカソンを兼ねたようなプロジェクトということでしょうか?
井本:まさにその通りです。できなければ評価は得られない、という厳しい環境でのプロジェクトでしたが、学生たちは非常に頑張ってくれました。実際の企業とコラボレーションし、発表する機会は緊張感もありますが、貴重な経験となりました。
樋口:学生にとっても企業にとっても、非常に有益な取り組みですね。今回の内容はデナリパムさんのXアカウントをフォローすれば見られるのでしょうか?
井本:はい、そうです。私たちのXアカウントをフォローしていただければ、詳細な内容やプロジェクトの進捗を確認できます。ぜひご覧ください。
――SNSなどをフォローしていただければ、Facebookなどでも内容を見られますので、ぜひチェックしてみてください。ありがとうございます。技術的に企業が発信できるよう伴奏され、メタバースやARでの体験を提供されているとのことですが、これらはすでに実装されているのでしょうか?
井本:はい、実際に生徒が作っています。今ご覧いただけるのは数年前にコロナ禍で実施した学園祭のメタバース版です。当時の学園祭をメタバース内で行い、ライブモデリングやライブペインティング、漫才など様々なコンテンツを提供しました。司会者やプレゼンターには声優志望の学生が参加し、リアルな体験を提供しました。
――それは素晴らしいですね。メタバースやVR、ARの技術がどんどんリッチになっていると感じます。私もニュースでイベント情報を発信していますが、メタバースやVR、ARに関する情報が増えてきています。リアルとメタバースが共存するイベントが当たり前になってきているのを実感します。
井本:そうですね。メタバースに関しては展示会と連動する形でよく活用されています。コロナ禍では代替的な役割を果たしましたが、今では補完的な役割も担っています。時間や場所に制約されずにイベントを開催できるという利点があります。しかし、メタバースのデファクトスタンダードはまだ確立されていません。どのプラットフォームが主流になるかはまだ分からない状況です。
――確かに、プラットフォームが多岐にわたっているため、一概にどこが主流かは言えませんね。しかし、技術が進化し続けているのは確かです。
井本:その通りです。私たちが教えている技術は、ブラウザだけでAI、AR、メタバースを体験できるものです。特別なハードウェアがなくても、ブラウザがあれば参加可能です。こうした技術が広がることで、イベントの表現方法も多様化しています。
――それは素晴らしいですね。リアルなイベントとデジタル技術の融合が進んでいるのを感じます。今回ご用意いただいているイベントでの技術活用例をぜひご紹介いただけますでしょうか?
井本:もちろんです。実際に山岳連携プロジェクトの事例をご紹介させていただきます。では、画面を共有させていただきますね。
――はい、お願いします。
井本:ありがとうございます。こちらが山岳連携プロジェクトの内容です。このプロジェクトは複数の学校と企業が連携して行ったもので、企業から提供されたテーマに基づいて学生たちが取り組みました。2月3日に発表会があり、すべてのデザインやプレゼンテーションは学生たちが担当しました。
――具体的にはどのような技術発表があったのでしょうか?
井本:今回のプロジェクトでは、東洋機械金属株式会社様の100周年を記念して、ホームページの改善をテーマに取り組みました。学生たちはメタバース、VR、AIの技術を活用し、ホームページを完全にメタバースに変える提案を行いました。また、大きな製品をデジタルツイン化し、仮想空間で体験できるようにしました。
――それは学生たちにとっても企業にとっても有益な取り組みですね。デナリパムさんのXアカウントをフォローすれば、この内容を見ることができるのでしょうか?
井本:はい、私たちのXアカウントをフォローしていただければ、詳細な内容やプロジェクトの進捗を確認できます。ぜひご覧ください。
――それでは、SNSなどをフォローしていただいて、詳細をご確認ください。最新技術を活用したイベントの展望を伺えて、とても興味深かったです。ありがとうございました。
井本:ありがとうございました。
――いありがとうございます。ではビジョンコントローラーという仕組みをご紹介したいと思います。今、画面の準備をしていますので、少々お待ちください。はい、画面共有させていただきます。これがビジョンコントローラーです。これは、動画が流れるサイネージなんですが、手をかざすと映像が動き、指をつまむと操作できるようになっています。
井本:例えば展示会などでこのシステムを使うと、人が集まりやすくなり、自然とコミュニケーションが生まれます。このシステムは四国の県庁にも導入されており、実績もあります。カメラだけを使用していて、今配信しているノートパソコンは7年前のものですが、それでも十分に動作します。
――なるほど。カメラとセンサーを使ったシステムなんですね。
井本:はい、カメラだけで動作します。ブラウザだけあれば、このサイネージを作ることができるんです。今では2万円くらいの小型ノートパソコンでも動作可能です。オンラインサービスとしても提供しており、愛媛県庁などに導入されています。
――それはすごいですね。どういったオーダーからこのシステムが生まれたのですか?
井本:これは研究開発から生まれたものです。具体的な理由は思い出せませんが、アイデアとして様々な用途が考えられる技術です。メタバースの話と同様に、技術があると、それに対するアイデアもどんどん生まれます。
――そうですね。技術があると、いろいろなアイデアや新しい伝え方が生まれる可能性が広がりますね。
井本:その通りです。今回の山岳連携プロジェクトでも、学生たちにAIやメタバース、VR、ARの技術を教え、ビジネスコンセプトの作成やプロジェクトの実施を行いました。1年のカリキュラムの中で、前期に技術を学び、後期にそれを応用して製品を作り、販売するという形です。売れなかったら点はないという厳しい評価基準ですが、その中で学生たちはテーマに沿った形で取り組んでいます。
――それは素晴らしい取り組みですね。実際の企業と連携してプロジェクトを進めることで、学生たちも実践的なスキルを身につけることができるのは貴重な経験だと思います。
井本:はい、そう思います。AIで何か驚くようなものを作ってくれたらと思っていますが、自分ができないことを学生に求めるのは難しいですね。今回も学生たちはよく頑張ってくれました。
――でも、そういった今お話があったようなテーマに沿って、カソというか、そういったところを持っていくのも良いのかなと考えています。そういったイベントもまた企画できたらなと思っています。その時は是非、一緒にご協力いただけたら嬉しいです。当社はそういった道具を山ほど持っていますので。
――ありがとうございます。まるでおもちゃ箱をもらったような感じで、そこから何かを探して遊んでいくのは、自由にやっていくと楽しい世界になっていくと思います。最後に、これから井本さんが控えている活動や、皆さんが体験できるようなイベントがあれば教えてください。
井本:はい、ありがとうございます。画面を少し共有させていただきます。実は、ここ大阪南港のATCで、3月22日にセミナーをさせていただきます。今、画面共有しているのはTwitterの画像ですが、大阪電子専門学校で私が顧問をさせていただいているところです。そこにデナホバーという、5万円程度の材料費で100kgの荷物を運べるインホイルモーターを使ったロボット技術を共有し、ロボットの授業を行っています。
――へえ、それはすごいですね。
井本:はい、その授業の成果として、こんな感じでロボットができました。それを大阪市のセミナーで、皆さんに見ていただこうと思っています。また、この小型のIoTデバイスを使って遠隔操作するワークショップ兼セミナーも行う予定です。3月22日の15時から18時に予定しています。まだ大阪市のページができていないので、TwitterやFacebookで情報を更新しますので、よろしくお願いします。
――ありがとうございます。是非、デナリパムさんのXをフォローして、アップデートをチェックしてください。最先端のワクワクするようなお話をありがとうございました。
井本:ありがとうございました。
――改めて、本日のゲストは株式会社デナリパム創業者兼代表取締役の井本直正さんでした。ありがとうございました。
井本:ありがとうございました。
――デモもしていただき、最新の技術を体験する機会も大阪で3月にあるようなので、是非チェックしてみてください。30分お付き合いいただき、ありがとうございました。また来週も配信しますので、是非ご視聴ください。ありがとうございました。