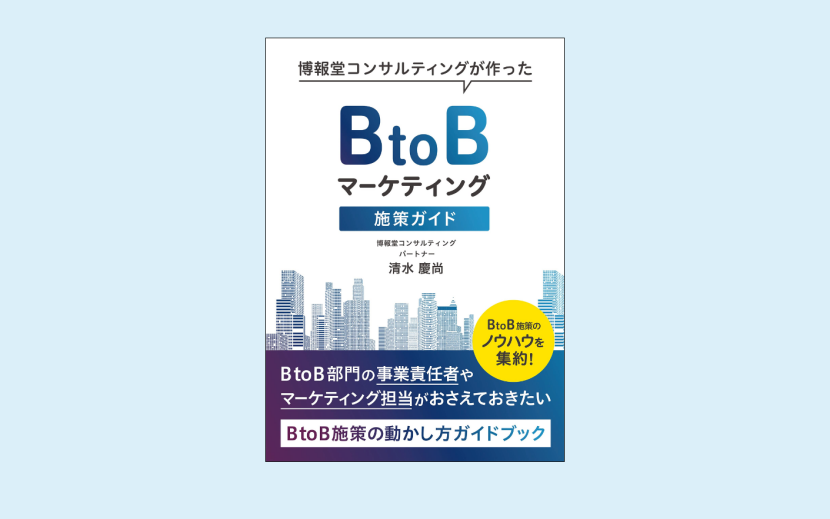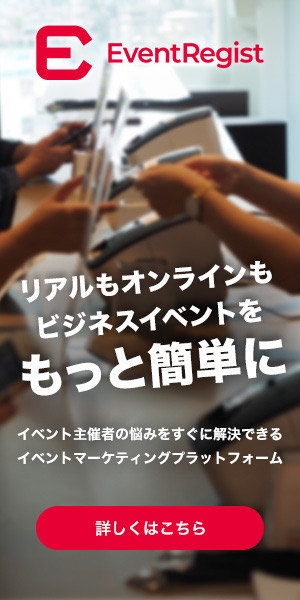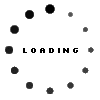どうせなら楽しく行こう。3000人超えクリエイターネットワークで企業プロデュース:ラフロワ合同会社 野呂翔悟 さん
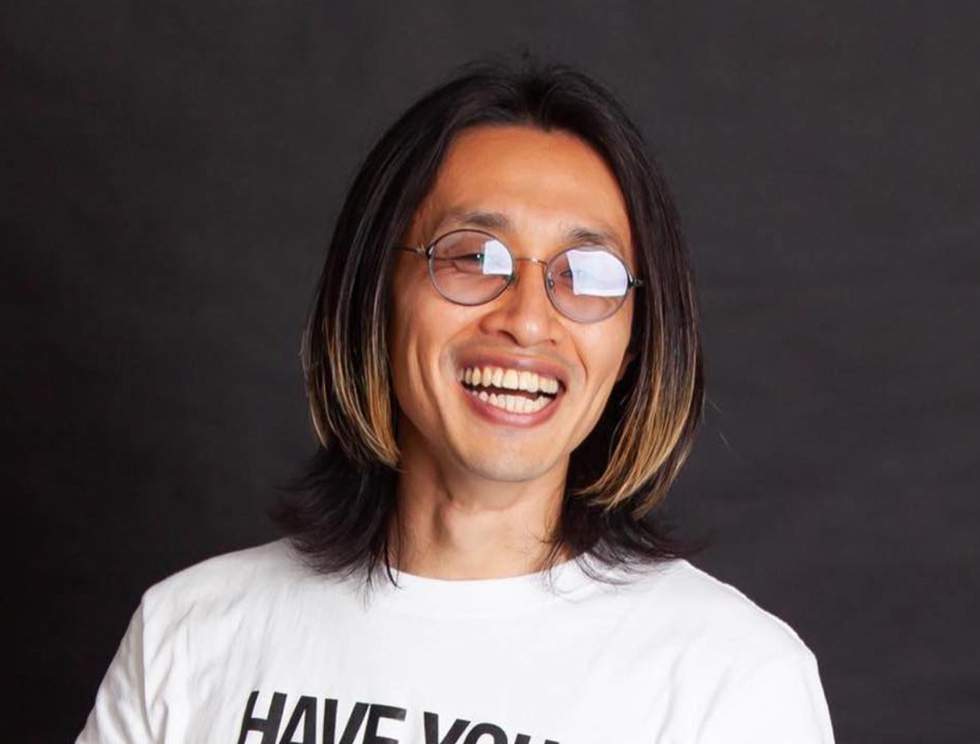
コースケよーこのミュートを解除 第141回 2024年2月16日(金)12:00〜
アーティストと企業のコラボレーションで、多くの人に楽しんでもらえるコンテンツを生み出していくことで、新たな価値を生み出しているLaflowa,LLC(ラフロア合同会社)の野呂翔悟さんに、アートを活用した、SNSマーケティング支援、コンサルタント、コンテンツ制作、イベント等のプロモーション企画などの取組みについておうかがいします。アートとイベントと企業と人の関係について一緒に考えましょう。
ゲスト:ラフロワ合同会社 野呂翔悟 さん
日本におけるアートシーンを活性化し、日本文化の発展、世界平和への貢献を目指します。Laflowa,LLCは、3000人を超えるクリエイターネットワークを基盤としたアート・エンタメコンテンツカンパニー。
日本最大級のSNSアートメディア 「KEIVI-軽美術部-」 @keivi.jp を運営。美術のJ-popカルチャーを創るべく日々企み中。
Laflowa,LLC代表。
動画URL:https://youtu.be/4fmRwTvdIIY
文字おこし
(自動文字おこしによるトークの概要・誤字脱字あります)
皆さんこんにちは、イベントマーケティングのよーこです。
コースケ:こんにちは、イベントレジストのコースケです。今日は2月16日金曜日、141回目の「コースケ・よーこのミュートを解除」が始まりました。この番組は、イベントレジストのヒラヤマコウスケさんとイベントマーケティングの樋口陽子が、イベントの中の人やプロをゲストにお呼びしてお話しする番組です。その道のプロだからこそ語れるリアルな価値やイベントの魅力をお話しいただきます。
――ということで始まりましたが、何回か前に少しお話ししたんですけど、最近私のマイブームでですね、去年彼女と一緒に群馬、高崎の先にある芸術祭に行ってきました。アート鑑賞のような1日の旅行体験をしてから、アートイベントにすごく興味を持つようになったんです。
――それは素晴らしいですね。アートイベントってどんな感じだったんですか?
――それが本当に素晴らしくて、アーティストの方々がどのように生活を成り立たせているのか、イベントの仕組みがどうなっているのか、すごく気になってます。
――確かに、アートと経済活動の両立って難しそうですもんね。
――そうなんです。そんな知らない世界を紐解いていただくために、本日のゲストをお呼びしております。ラフロア合同会社の野呂翔悟さんです。こんにちは、野呂さん。
野呂:こんにちは、よろしくお願いします。
――野呂さんは、アーティストと企業のコラボレーションで、多くの人に楽しんでもらえるコンテンツを生み出していらっしゃるということですが、具体的にどのような活動をされているのかお聞かせください。
野呂:はい、僕自身はアーティストではなく、アーティストに憧れて応援したいという気持ちでこの仕事を始めました。ラフロアという会社を立ち上げ、メディアを運営しており、現在17万人のフォロワーがいます。
――それはすごいですね。どのようにしてここまでの規模になったのですか?
野呂:7年間、イラスト系のアーティストをキュレーションして紹介し、ネットワークを広げてきました。現在は数千人のアーティストとつながり、さまざまな事業を展開しています。
――なるほど、芸能事務所のような機能を持つ会社ですね。具体的にはどのようなプロジェクトを手掛けているのですか?
野呂:例えば、企業とアーティストのコラボレーションで、商品のパッケージデザインやプロモーションビデオを制作しています。こうしたプロジェクトを通じて、アーティストの作品が広く認知されるよう努めています。
――非常に興味深いです。アーティストと企業のコラボレーションは、どのように始めるのですか?
野呂:企業からの依頼や、こちらから提案することもあります。双方がWin-Winの関係を築けるよう、丁寧にコミュニケーションを取ることが大切です。
――今日はたくさんの興味深いお話をありがとうございました。今後の活動も楽しみにしています。
野呂:こちらこそ、ありがとうございました。
――ところで、アートイベントに参加したことでアーティストの生活に興味を持たれたとおっしゃっていましたが、具体的にどのような点が気になりましたか?
――アーティストがどのようにして生計を立てているのか、またアート作品の制作過程や販売方法など、具体的な経済活動について知りたいと思いました。
野呂:確かに、アーティストの経済活動は一般的にはあまり知られていません。私たちはアーティストと企業の間に立ち、コラボレーションを通じて新たな価値を創出し、その過程でアーティストの経済的な安定をサポートしています。
――企業とアーティストのコラボレーションによって生まれた成功事例について教えていただけますか?
野呂:はい、例えばある飲料メーカーとのコラボレーションで、アーティストがデザインした限定パッケージを制作しました。これがSNSで話題となり、売上が大幅に増加したケースがあります。また、プロモーションビデオの制作でも、アーティストの独自の視点と創造力が企業のブランドイメージを強化することに成功しました。
――それは素晴らしいですね。アーティストの作品が多くの人に届くことで、企業も大きなメリットを享受できるわけですね。
野呂:そうですね。アーティストの作品が広がることで、企業のプロモーション効果も高まり、双方にとって非常に有益な関係が築けます。
――今後、アートとビジネスの融合でどのような展開を考えていますか?
野呂:これからもアーティストの可能性を広げるために、新しい形のコラボレーションを模索していきたいと思っています。また、アーティスト自身が主体的にビジネスに参加できるような支援体制を整えることも重要だと考えています。
――芸能事務所的な機能を持った会社という感じでしょうか。アーティストを抱えるYouTuber事務所に近いイメージですね。
野呂:はい、そうですね。インフルエンサーマーケティングに近い感じです。たくさんのインフルエンサーを抱えているようなイメージです。
――そのメディアにはイラストレーターさんが何名くらい登録しているのですか?
野呂:うちはエージェント的な感じで、あまりマネジメントはしていないんですが、提携という形でやっています。メディアに掲載しているイラストレーターだけでも1000人弱くらいいますね。
――すごいですね。SNSで人気のイラストレーターもここ5年6年で増えていますよね。
野呂:はい、そうですね。多分、うちは一番有名、というか、一番知っていますね。メディア名が「KEIVI-軽美術部-」といいます。軽音部みたいな感じで。
――じゃあ、SNSの発展で新しく生まれた業態ということですね。10年前だと作れなかった業態でしょうか。
野呂:おっしゃる通りです。元々イラストレーターというと、いろんなパターンがありますが、最近では漫画やイラストっぽい作品を描くアーティストが増え、それにファンがついてインフルエンサーになるケースが増えています。僕はそれをキュレーションして、いろんなイベントやプロモーションを企画して盛り上げています。
――アーティストと企業のコラボレーションも多いですね。最近の具体的な事例を教えていただけますか?
野呂:はい、例えば音楽界隈でのイラストレーターとのコラボが増えています。アートと音楽の相性が良くて、最近ではイラストレーターとミュージシャンのコラボイベントも増えています。
――そのイラストレーターたちをどのようにして見つけてきたのですか?
野呂:地道に1人1人DMを送るなどしてやっています。本当に新しい才能がどんどん出てくるので、チェックを欠かさずにしています。
――アートシーンを日本でももっと盛り上げたいという気持ちがあったのでしょうか?最初はどのような動機で始めたのですか?
野呂:特に危機感があったわけではなく、もっと絵を楽しんでもらいたいというシンプルな気持ちからです。美術やアートは敷居が高いと感じる人も多いですが、スマホで見られる漫画っぽい絵もアートとして楽しめると、もっと身近に感じられるのではないかと思いました。
――なるほど、身近なものにしていくためにSNSを活用しているんですね。
野呂:そうです。SNSを通じてアートの楽しさを広げています。
――野呂さん自身の原体験として、アートに目覚めたきっかけは何かありますか?
野呂:特別な体験はありませんが、おじいちゃんが絵の先生だったんです。僕は鹿児島出身で、祖父が桜島の絵を描いていました。子供の頃はあまり興味がなかったんですが、企業を立ち上げる際にその思い出も影響していると思います。
――DNAにアートが組み込まれているんですね。
野呂:そうですね。ティストの方は大変だろうなという漠然とした思いがありました。経済基盤をきちんと持って活動ができる世の中になればいいなと思って、活動を続けています。
――確かに、スポーツ選手のようなトップクラスの人以外、どうやって食べているのだろうというのが一般的な認識ですよね。
野呂:そうですね。僕もクリエイターエコノミーを作りたいというのが目標です。
――そういう原体験を多くの人が持つためには、もちろんSNSでの交流も大事ですが、例えばアーティスト本人に会えるイベントなどもされているのですか?
野呂:はい、結構イベントもやっています。特に似顔絵イベントが人気で、「顔東京」という名前で商業施設でやっています。イラストレーターさんが描く似顔絵が好評で、行列ができることもあります。握手会のような感じで、ファンの方に直接会えるのが魅力です。
――インフルエンサーとしての力も発揮されているんですね。
野呂:そうですね。最初はファンが来て盛り上がるのですが、例えばサントリーさんのジムビームのイベントで、カップに似顔絵を描くという企画も行いました。これはファンだけでなく、一般の方にも好評で、5日間でずっと行列ができる人気イベントになりました。似顔絵を描いてもらうことで自己承認欲求が満たされるようで、パーソナライズされた商品はとても喜ばれます。
――そういったイベントを通じて、アートをもっと身近に感じてもらうことができるんですね。
野呂:そうですね。イベントでの似顔絵は、来場者にとって非常にパーソナルな体験となります。イラストレーターの方々も多く参加していただいて、日替わりで色々な方に描いてもらえるようにしています。
――すごいですね。日替わりで色々なイラストレーターの方が参加するんですか?
野呂:はい、そうです。例えば20人ほどのイラストレーターさんに日替わりで来ていただきます。このようなイベントでは、イラストレーターさんも自分のスタイルや特徴を活かした作品を提供できるので、非常に盛り上がります。
――参加するイラストレーターさんはどのように選ばれるのですか?
野呂:その時の企画に合ったイラストレーターさんに声をかけます。例えば、若い女性に人気のあるイラストレーターや、特定のキャラクタースタイルが得意な方など、イベントのテーマやターゲットに合わせて選んでいます。
――なるほど。イベントごとに適したイラストレーターさんを選ぶのですね。
野呂:はい、そうです。そして、参加したイラストレーターさんたちも、実際にファンと直接触れ合える機会をとても楽しんでいます。SNSでの活動とリアルイベントでの交流がうまくシナジーを生んでいます。
――ファンと直接触れ合えるのは、イラストレーターさんにとっても大きなモチベーションになりますね。
野呂:そうですね。ファンの方々も、SNSで見ていたイラストレーターさんに直接会えるということで、非常に喜んでくれます。そういった交流の場を提供することで、さらにアートの魅力を広げていけたらと思っています。
――そのような取り組みを通じて、アートがより身近なものになっていくといいですね。
野呂:はい、まさにその通りです。アートを通じて人々が笑顔になり、日常が少しでも豊かになれば、それが一番の喜びです。これからも、アーティストと企業、そしてファンをつなげる架け橋として、様々な取り組みを進めていきたいと思っています。
――なるほど。渋谷だからこそ、若いユーザー層に訴求できる面もあるのですね。
野呂:はい、まさにそうです。ユーザー層でいうと、20〜30代を狙いたいという話でしたが、感度が高い30代の人も、イラストっぽい作品をアートとして数十万円で購入することもあります。アート界隈でも反応が良かったですね。
――確かに、そういう人たちは新しいものやユニークなものに敏感ですもんね。イベントの効果も大きかったのでは?
野呂:そうですね。SNSでの発信力も相まって、イベントの認知度や集客力が向上しました。また、参加アーティストや企業側の満足度も高く、今後の継続的な取り組みへの期待も大きいです。
――企業とアートのコラボレーションって、これからますます可能性が広がりそうですね。
野呂:そう思います。特にSNSの力を借りることで、より多くの人にリーチできるようになりますし、アーティストたちも自分の作品を広く知ってもらえる機会が増えます。これからもいろんな形でアートと企業をつなげる取り組みをしていきたいです。
私も自分を描いてもらいたいという気持ちがあったり、例えば飼っている猫を描いてもらいたいというのもあります。身近なものをイラストにしてずっと置いておきたいなという気持ちもありますね。これからの成長市場で言うと、インバウンドの需要も大きいです。多くの海外の方々は日本のイメージとしてアニメやイラストを持っています。彼らが日本に来て、アニメや漫画のようなイラストを見つけるととても喜びます。イラストはアニメや漫画とはまた違ったジャンルですが、非常に魅力的なコンテンツだと思います。
イベントでも外国人の方々がたくさん来て、漫画やイラストを楽しんでいました。日本自体のイメージが漫画という部分が大きいので、それを活かして海外展開を進めたいと思っています。ストーリーズの事例を見ても、動画とのコラボが非常に効果的です。イラストは静止画のイメージが強いですが、tiktokやYouTubeなどの動きがあるプラットフォームと組み合わせると新しい表現が広がります。
例えば、キナさんとのミュージックビデオでは、イラストと音楽のコラボが非常に面白かったです。イラストと音楽、動画の表現がどんどん広がっています。イラストをメインに活動していますが、ショート動画やYouTubeなどの動画コンテンツも多く手がけています。イラストだけでなく、漫画風のコンテンツも増えており、幅が広がっています。
聞いている方々も、いろんなコラボを思い描いていると思いますし、私自身もアイデアがたくさん浮かんでいます。しかし、時間が来てしまいましたので、野呂さんが直近でどのような活動をされているのか教えていただけますか?
野呂:ありがとうございます。直近の活動としては、池袋のサンシャインシティが運営する「トラリウム」とコラボしています。池袋をテーマにしたコンテストを実施し、優勝者の個展が明日から始まります。メタバースでも展示を行い、デジタルアートが体験できる企画です。
直近で言うと、ちょうど明日からなんですけど、サンシャインシティ池袋のサンシャインシティさんが運営している「トラリウム」というスペースカフェとコワーキングスペースがあります。3階にありまして、そことコラボして今イベントを実施しています。
池袋グループ店という池袋をテーマにしたコンテストを実施し、その中で優勝された方の個展が明日から始まります。
――おお、そうなんですね。コワーキングスペースでの個展ですか?
はい、フリースペースがメインなんですけど、そこに作品が10点展示されます。また、クロスコさんというメタバースの会社さんとコラボして、メタバースでも鑑賞できるようになっています。
――面白いですね。確かにそういうスペースへの集客というのも含めて、イラストを実際に見たいというニーズに応えるのは良いですね。原画が見れるんですか?
ええ、デジタル印刷された作品がメインですが、一部キャンバス作品もあります。さらにメタバース空間でデジタルアートが体験できるようになっています。
――それは変えたりもするんですか?
今回は販売はしていなくて、グッズ販売のみです。
――グッズがあるんですね。確かに私も芸術祭に行った時にグッズを買いましたが、持ち歩きたいという気持ち、分かりますね。
はい、ぜひ池袋近くの方は明日から今月28日まで開催中なので、足を運んでいただきたいと思います。また、野呂さんにコラボしたい方は、メディアをフォローしてDMなどで連絡を取っていただければと思います。今日は本当に知らない世界のいろんなお話を伺いまして、ありがとうございました。
――改めて、本日のゲストはラフロア合同会社の野呂翔悟さんでした。ありがとうございました。