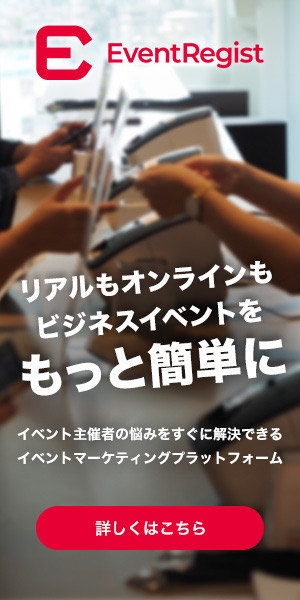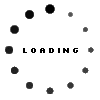ボードゲーム達人で「遊び配達人」として活動する栗原達也さんをゲストに迎え、ボードゲームの魅力とその広がりについてお話を伺いました。聞き手はイベントマーケティング編集長の樋口陽子さんとイベントレジストのヒラヤマコウスケさんです。
栗原さんは、ボードゲームの会社で働く傍ら、個人の活動として遊びが足りない場所に遊びを届ける「遊び配達人」として活動しています。ホテルでの室内アクティビティや地方自治体のイベントなどで、依頼に応じてボードゲームを提供し、遊びを広めています。
近年、ボードゲームカフェが都内で増加しており、関東内だけで100か所近くあります。カフェには何百種類ものボードゲームが揃っており、スタッフがゲームの選び方や遊び方を教えてくれます。ボードゲームの楽しみ方は個人で購入して遊ぶだけでなく、オープン会と呼ばれるイベントで知らない人同士が集まって遊ぶこともあります。
栗原さんは、団地コミュニティの形成にボードゲームが役立つと考え、自ら団地に住んでイベントを開催しました。最初は少人数の参加でしたが、次第に参加者が増え、団地の公園でのイベントには40人が集まりました。小学生から高齢者まで幅広い年齢層が参加し、世代を超えた交流が生まれました。
イベントの共通点としては、子供に「面白い」を伝えられるかどうかが重要です。子供に遊びを教えるのは大人であり、大人が遊ぶことが子供の遊びに繋がると栗原さんは考えています。子供が楽しそうなイベントを企画すれば、自然と家族全員が参加します。
栗原さんへの依頼は自治体やイベント企画者からが多く、個人でも連絡を受け付けています。最近では、DIYでオリジナルのゲームを作り、それを提供することも増えています。
文字おこし
(自動文字おこしによるトークの概要・誤字脱字あります)
皆さんこんにちは。イベントマーケティングのよーこです。イベントレジストのコースケです。1月26日金曜日、138回目の「コースケ・よーこのミュートを解除」が始まりました。この番組はイベントレジストのヒラヤマコウスケさんとイベントマーケティングの樋口陽子が、イベントのプロフェッショナルをゲストに迎えてお話しする番組です。プロだからこそ語れるリアルな知識やイベントの魅力をお伝えします。
さて、突然ですが、ヒラヤマさんはボードゲームをされたことはありますか?子供の頃にはよくやっていましたが、大人になるとなかなか機会がなくなりますね。一般的には多くの方がそう感じているのではないでしょうか。私は実は今でもボードゲームを楽しんでいます。例えばエバーデールやドイツのボードゲームなど、2人用や家族用のゲームをやっています。
前回はEスポーツイベントについてお話しましたが、今回はボードゲームについてお話します。Eスポーツでは親子やチームのコミュニケーションが強調されますが、アナログなボードゲームにはまた違った魅力があります。人生ゲームやモノポリーを思い浮かべる方も多いでしょうが、実際にはもっと多様な種類があります。
本日のゲストは「遊び配達人」として知られる栗原達也さんです。こんにちは、栗原さん。ご無沙汰しております。後ろに映っているのはゲームですか?はい、少し乱雑に置いてありますが、今日はボードゲームの世界についてお話しします。栗原さんは「遊び配達人」として活動されているということですが、具体的にはどんな活動をされているのでしょうか?
遊び配達人として、遊びが足りないところに遊びを届ける活動をしています。ホテルでの室内アクティビティや地方自治体のイベントなどで、依頼に応じて遊びを提供します。ボードゲームは人数や年齢に合わせて選ぶことができ、その場を盛り上げる効果があります。ゲームの種類も多様で、人生ゲームやチェスなどのボードゲームだけでなく、カードゲームやトランプなども含まれます。
最近ではテレビ番組でもゲームを紹介することが増えてきましたが、選ぶゲームが重要です。年間で1000タイトルもの新作ゲームが登場し、国内外から多くのゲームが入ってきます。人数や年齢に合わせて適切なゲームを選ぶことが、楽しさを引き出すポイントです。
さらに、ボードゲームの説明をするファシリテーターの存在も重要です。栗原さんは現場でゲームの説明をする際、短時間でわかりやすく説明することを心掛けています。ゲームのルールを細かく伝えることも大事ですが、楽しさを優先してルールを柔軟に解釈することもあります。相手やゲームに応じて、適切な伝え方を工夫しています。
その場を読む力も必要ですね。ゲーム自体の魅力を引き出すためには、直感型のゲームと理論派のゲームをうまく選ぶ必要があります。説明するよりも、やってみた方が早いこともあります。「とりあえず1回やってみましょう」という感じで進めることもあります。
ボードゲームを楽しむカフェも都内各地で盛り上がっていますね。今、関東内、特に都内だけで100か所近くあると言われていて、銀座の店舗数と同じぐらいの数です。カフェでゲームをするのは気軽にできて良いですよね。ゲームもその場にあり、教えてくれるスタッフもいるので、食べ物の持ち込みも自由な場合が多いです。ジェリージェリーカフェがアクセスしやすい場所に多くの店舗を構えていて、渋谷や新宿、池袋などにあります。
そのカフェには何百種類ものボードゲームが揃っていて、スタッフに「盛り上がるゲームはどれですか?」と聞けば教えてくれます。ボードゲームをやってみたいけれど、どこでできるのか、どれを買えばいいのかわからない方にはお勧めです。
ボードゲームの購入は、オンラインゲームやテレビゲームのカセットを買うのとは違い、新しいゲームを買っても一人では遊べません。カフェで仲間とやるのが一般的です。もちろん個人で買って、仲の良い人と遊ぶこともありますが、オープン会と呼ばれるイベントで知らない人と一緒に遊ぶこともあります。
オープン会では同じ趣味の友達を見つけることもでき、釣りやサウナのように、多人数で楽しむ場です。私はイベントを立てることもありますが、基本的には依頼を受けて出向くスタイルです。
最近の依頼は自治体やイベント企画者からが多いです。例えば、団地のコミュニティ形成にボードゲームが役立つと考え、URさんに依頼をお願いしていましたが、依頼が来なかったので自分で団地に住んでイベントを開催しました。最初は6人しか来なかったですが、2回目には団地の公園で40人ほど集まりました。
参加者の年齢層も幅広く、小学生から高齢者まで多様です。団地の全ポストにチラシを入れてもらうなど、地域の協力があり、盛り上がりました。他のURさんからも依頼があり、他の団地でもイベントを開催しています。URさんは自治体とも繋がっているので、自治体のイベントにも呼ばれることが多いです。
やっぱり子供が遊んだり楽しむコンテンツがなかなか作れないんですよね。今、公園でボール遊びが禁止されているところも多く、子供が何をして遊ぶのか困ってしまいます。飲食関係のフードを集めるのは比較的容易ですが、子供が楽しむためのコンテンツを実際に提供するのは大変です。実際にそのような活動をしている人が少ないのも理由の一つです。
そのため、子供の賑やかしとして声をかけていただくことが多いです。第2回目のイベントではどういうゲームで遊ばれたのでしょうか?比較的簡単なゲームが多かったですね。例えば、20人で一斉にやるのではなく、グループに分けて、1回10分から15分で終わるゲームを次々と用意しました。その時は40種類ほどのボードゲームを準備しました。
毎年1000タイトルもの新作ゲームが出ているというのも驚きですが、新たな遊びを見つけるのも面白いですね。ゲームをやることとイベント化することには違いがありますが、遊び配達人の栗原さんが届けることでイベント企画とボードゲームの共通点は何でしょうか?
共通点としては、子供にどれだけ「面白い」を伝えられるか、提供できるかだと思います。遊び配達人として活動するのは、子供に遊びが足りていないと感じたからです。子供に遊びを教えるのは結局大人なので、大人が遊ぶことが子供の遊びに繋がると思っています。
イベントの課題としては集客がありますが、子供が行きたいと思えるイベントを企画すれば、大人も一緒に参加します。昔から言われているように、女性が楽しめるイベントには男性もついてきます。子供が楽しそうなイベントを企画すれば、自然と家族全員が参加します。
遊び配達人の栗原さんに依頼すれば、個人の活動でも自治体からの依頼でも、ターゲットに合わせた内容でゲームを提供してくれます。最近はDIYでゲームを作ることもしており、オリジナリティのあるゲームも提供できます。
遊びを求めている方々は、InstagramやX(旧Twitter)、Googleで「栗原達也」とカタカナで検索していただくと、栗原さんのプロフィールがトップに出ますので、そこから連絡してください。
今日は、知らなかった世界について深くお話を伺い、ありがとうございました。改めて本日のゲストは遊び配達人の栗原達也さんでした。ありがとうございました。